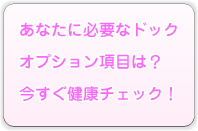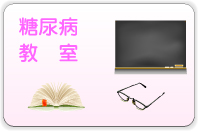リハビリテーション科
診療内容
リハビリテーション診療は、暮らしや社会生活における『困りごと』をうかがうところから始まります。
困りごとの原因が治療しうる病気や外傷であれば、適切な診療科に紹介いたします。
障害とともに生きていくべき状況であれば、身体機能の向上・環境調整(道具の導入や環境整備)・支援体制の構築(介護・福祉分野との連携)を組み合わせ、困りごとの軽減を目指します。
- 【外来診療】
- リハビリテーション外来
- 開業医の先生から紹介いただいた方、当院退院後の方に対し、医療保険を用いたリハビリテーションを提供しています。
(介護保険利用中の方は、医療保険を用いたリハビリテーションを受けることはできません。) - 装具外来(毎週金曜日)
- 足の裏の胼胝(たこ)・足の長さの違い等が、歩き方を崩し、膝や腰などに痛みを生じさせることがあります。
脳卒中後につっぱった歩き方を学んでしまうと、歩行能力が低下したり、転びやすくなったりします。
こうした症例に対し、適切な装具(短下肢装具・足底装具・靴など)を処方することで、運動効率の向上や、疼痛の軽減が得られる場合があります。
当科では、医師・理学療法士・義肢装具士・整形靴マイスターが適切な装具を検討し、処方しています。 - もの忘れ外来(毎週水曜日)
- 認知機能が低下し生活に支障が出ている方々に対し、原因検索および治療を行っています。
脳卒中や頭部外傷等により高次脳機能障害を生じた方々の診療も行っています。
自動車運転免許更新の際に認知機能低下を指摘され、精査を勧められた方の対応も行っています。
(ただし、当院に主治医がいる方に限らせていただいています。) - 【入院診療】 病院には、思いがけず病気や外傷を患った方々が集まっています。
- 急性期リハビリテーション
- 病気や外傷と闘っている時期に行われるリハビリテーションです。
治療の妨げとならない範囲で体調を整える(関節の拘縮を防ぐ・最低限の筋力維持を図る)ためのリハビリテーションを行います。
- 回復期リハビリテーション
- 急性期治療を終えた時点で、病前の生活に戻ることが困難な方々には、回復期リハビリテーションを受けることをお勧めしています。
身体機能の向上・環境調整・支援体制の構築を組み合わせ、「活き活きと生きる」ための具体策を検討します。
当院には回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟の2病棟が設置されています。
- 〔回復期リハビリテーション病棟〕
- 1日最大3時間、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)による積極的リハビリテーションを受けることができます。
国により入棟できる疾患が定められているため、誰でも利用できるわけではありません。
また疾患ごとに入院していられる期間が定められています。
- 〔地域包括ケア病棟〕
- 1日40分以上、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)によるリハビリテーションを受けることができます。
入棟できる疾患の制約はありませんが、入院期間は2カ月以内と定められています。
当院では退院後の生活を見据え、安全に配慮しつつ早期からリハビリテーションを実施するよう心がけています。
当科の特色
- ボツリヌス療法
- ボツリヌス療法では、ボツリヌス菌が産生するボツリヌス毒素を用います。
ボツリヌス毒素は神経の末端と筋肉のつなぎ目部分に作用し、神経から筋肉に収縮信号が届くのを妨げます。
この結果、ボツリヌス毒素を打ち込んだ筋肉は弛緩します。
この治療法で使うボツリヌス毒素は極めて薄い濃度で、狙った筋にとどまるため、全身に回ることはありません。
また、ボツリヌス菌を打ち込むわけではないので、体内でボツリヌス菌が増殖するということもありません。
当科では、主として脳卒中後につっぱり(痙縮)が生じた方に対して施注しています。
つっぱりにより本来の下肢機能・上肢機能を発揮できなくなっている方々は意外と多く、適切なボツリヌス療法を行うことで、下肢機能・上肢機能の改善が得られることがあります。
機能回復のための鍵は、
・適切な筋に、適切な量のボツリヌス毒素を投与すること
・適切な運動療法を併用すること
・関節が拘縮していないこと
・患者本人に機能回復のための強い意志と理解力があること です。
当科では、理学療法士・作業療法士らと、施注の目的・施注すべき筋と施注量等を相談した上で実施しています。
治療効果を高めるため、ボツリヌス療法は地域包括ケア病棟に入院して行うことを推奨していますが、自宅で適切な自主訓練を行える方に対しては、外来でボツリヌス毒素を施注することもあります。
- 装具療法
- 装具外来の項をご覧ください。
医師紹介
| 氏名 | 役職 | 専門分野 | 専門資格/加入学会 |
| 山口 浩史 | リハビリテーション科科長 地域先進リハビリテーションセンター長 |
リハビリテーション科 | 専門資格 |
| 日本専門医機構リハビリテーション科専門医 日本認知症学会専門医・指導医 日本義肢装具学会専門医 身体障害者福祉法第15条指定医 難病指定医 |
|||
| 加入学会 | |||
| 日本リハビリテーション医学会 日本脳卒中学会 日本義肢装具学会 日本ボツリヌス治療学会 日本高次脳機能障害学会 日本認知症学会 |